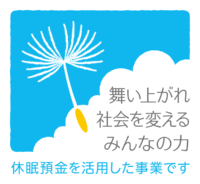一般社団法人さが・こども未来応援プロジェクト実行委員会(以下「さがっこ」)は、一般財団法人日本民間公益活動連携機構(略称:JANPIA)が実施する2024年度休眠預金事業通常枠の資金分配団体に選定されました。
以下の通り、選定された事業内容に基づく事業を実施するための実行団体の公募・選定・助成を行います。公募要領を必ず全てご確認の上、ご申請をお願いいたします。
–公募にあたって–

近年、「経済的困窮」「不登校」「孤立」などの課題が複雑に絡み合い、支援を必要とする子育て世帯が増え続けています。かつては、血縁や地縁、学校といったつながりの中で相互に助け合いながら子育てをしてきましたが、そうした地域の支え合いの力が弱まってきました。それを補うようにこども家庭庁が設立され、支援制度や専門機関の整備は進んできたものの、現場ではまだまだ社会資源が足りていません。
たとえば佐賀県では、3年前に開設された児童家庭支援センターにおいて、毎月200件を超えるショートステイや一時保護の受け入れ要請があり、やむなく断らざるを得ないケースも増えています。あるスクールソーシャルワーカーは「毎日50件以上の相談があり、さばくだけで精一杯」と話します。
現場からのヒアリングの中で、私たちは3つの大きな問題があることに気づきました。
- 問題1 孤立した家庭や支援につながりにくい層へのアプローチの困難さ
- 問題2 支援を必要とする世帯の多さに対して、人手も時間も足りない現状
- 問題3 複雑な課題を単一の機関だけで解決することの限界
です。
こうした声を受け、
「専門機関が役割を果たせる地域をどう作るのか?」
「忙殺される現場を誰がどう支えるか?」
という2つの問いが浮かびました。今、私たちには行政や専門機関だけでは対応しきれない現状に対し、市民や民間団体もともに支える新たな地域社会をつくることが求められています。
さがっこでは、休眠預金活用事業を利用させていただき、佐賀県内の3つのエリアで諸課題を乗り越えながら一緒に向き合ってくださる方のご応募を、心よりお待ちしております。
一般社団法人 さが・こども未来応援プロジェクト 代表理事 山田健一郎
なお、以下に、公募要領から「本助成事業の概要」、「公募期間・申請方法・申請に必要な書類」「選考基準等」を抜き出し掲載しておりますが、必ず公募要領全文をご確認の上、ご応募の検討・準備をお願いいたします。
また、個別相談会を用意しております。ぜひ、ご活用いただけますようよろしくお願いいたします。
本事業の概要
本助成事業の概要は以下の通りとなります。
事業名
「行政」×「専門機関」×「地域資源(市民)」による地域子育て包括支援事業
〜子育て世帯や子どもを支援する行政・専門機関の活動に市民が主体的に関わり支える〜
事業の概要
本事業は、佐賀県内において、支援を必要とする子育て世帯への支援を「量」「質」両面で強化するため、市民・地域団体と行政・専門機関が連携し、地域ぐるみで支える体制を構築することを目的としています。
現在、「経済的困窮」「不登校」「孤立」など、子育て世帯が抱える課題は複雑化・深刻化しており、行政や専門機関だけでは十分な対応が難しい状況にあります。現場からは、「つながれない家庭」「多すぎる支援ニーズ」「課題の複雑さ」という3つの壁があると感じています。地域の力を生かした包括的な支援体制の構築が急務となっています。
このような背景から、本事業では、社会福祉協議会やNPOなどの民間団体が主体となり、「行政」「専門機関」「地域資源(市民団体・ボランティア・寄付者等)」が協働するチームを、県内3つのエリアで立ち上げ、地域に根ざした支援活動を展開していきます。
実行団体の皆さまには、以下のような活動を担っていただくことを想定しています。
1)アウトリーチ事業
- 虐待の自覚がないなど行政ではつながりにくい家庭を見つけて、つながることで支援のきっかけづくり
- 保護者の精神疾患などが理由で見守りが必要な家庭と継続的につながり続ける
2)保護者の相談支援事業
- フードパントリー等の場を活用し、気軽に、主体的に参加する場を作り、受援を喚起し、非専門職を含めた相談受付体制の整備
3)居場所事業
- 不登校児童の居場所づくり
- ショートステイなど、保護者をレスパイトできる機能の提供
4)地域チームビルディング
- 他団体や支援者のコーディネート役としての調整
- 行政・専門機関・地域団体が連携する「地域包括支援チーム」の組成
5)地域の支援基盤整備
- 物資の流通体制づくり、寄付集め、政策提言など支援の持続性を高める取り組み
この事業では、単に活動を担っていただくだけでなく、地域における「支援のハブ」としての役割を期待しています。専門性や地域とのつながりを生かし、支援の谷間にある家庭や現場を支えるパートナーとして、共に活動を進めていただける団体の参加を心よりお待ちしております。
事業期間
2025年9月から2028年2月
ただし、助成開始時期は、選考、契約の手続きにより変更する場合があります。
採択予定実行団体数
3団体(3つのエリア)
事業費
- 総額 100,519,200円
- 1団体あたりの助成額 18,000,000~22,000,000 円を目安とする。
対象となる団体
- 日本全国の民間の非営利組織(特定非営利活動法人、一般社団法人、社会福祉法人等。任意団体は除く 任意団体を含む。)
困難な状態にある子どもと、その保護者の支援を、行政・社会福祉協議会・専門機関や他の地域資源と連携して事業を行う団体。
包括的に子育てや、子どもの養育を推進する地域を創っていく活動を行う団体
※専門機関とは
公的な福祉・教育サービスを行う団体や個人。
- 1団体1申請に限ります。
- 複数の組織が協働で事務局を担うコンソーシアム型の応募も可能です。その場合は体制図にその旨をご記載ください。ただし、その場合も主幹事となる団体 (民間の非営利組織に限り、法人格を有する団体とします)を決めて頂き、資金分配団体であるはその団体に対して助成金の支払いや契約手続き等を行います(主幹事団体以外の ガバナンスやコンプライアンスに関しては個別に調整いたします)。また、実行体制や意思決定のプロセスについて明確になっている必要があります。
対象地域
佐賀県
実現したいアウトカム
本事業では、「行政 × 専門機関 × 地域資源」の協働によって、支援が届きにくかった家庭や子どもたちに新たな支援のルートをつくり出すとともに、持続的な地域支援のしくみの構築を目指します。
短期アウトカム(当該事業の3年以内に目指す変化)
地域資源の活用によって、行政や専門機関の支援の「到達力(支援対象者数)」と「対応力(支援の質)」が向上します。
事業エリア内で行政・専門機関を支える地域資源(NPO・ボランティア・住民など)が組織的に活用され、「支援者を支援する仕組みができている」
具体的には
- 行政ではつながることが難しかった孤立家庭(行政拒否ケース等)に、地域のNPOや市民団体が介在することで接点が生まれ、専門機関による支援の開始が可能となる。
- フードパントリーや居場所などの「立ち寄りやすい機会」が増えることで、支援が必要な家庭が早期に発見・対応され、専門機関の対応が不要なケースが増える。
- 不登校の子どもが、地域の非専門職との関わりによって引きこもりに至らず、深刻化を防げるようになる。
- 専門機関同士や地域資源との連携が進み、複雑なケースへの対応や、支援対象者の受け入れ可能数が増える。
- 地域の支援人材・物資などのリソースが整備され、専門機関が家庭を地域へ安心して「つなぐ」ことが可能となる。
中期アウトカム(事業終了後も継続して見られる変化)
行政・専門機関の支援力が高まることで、子育て世帯や子どもたちの生活と成長に以下のような変化が見られます。
具体的には
- 保護者の無理解や拒否により支援が届いていなかった子ども(虐待・ヤングケアラー等)にも支援が行き届くようになり、深刻な孤立家庭が減少する。
- 専門機関が1家庭にかける支援の時間が確保され、課題解決に至る家庭の割合が増加する。
- 社会的孤立に陥りがちな若者(不登校・引きこもり等)が地域で役割を見つけ、自立へとつながる。
- 子育て家庭が、必要なときに必要な支援にアクセスできるようになり、孤立や問題の深刻化を防げるようになる。
長期アウトカム(持続的な社会的変化)
地域全体で子育てを支える仕組みと文化が根づき、持続可能な地域での包括的な支援体制が構築されます。
具体的には
- 市民や団体の参加が広がり、地域全体で子育てを支える「共助の文化」が定着する。
- 当事業のノウハウが横展開され佐賀県全域で行政・専門機関を支える地域資源(NPO・ボランティア・住民など)が組織的に活用され、「支援者を支援する仕組み」が地域に組み込まれる。
こうした連携モデルが事業実施エリアに定着し、佐賀県社会福祉協議会等と連携して県内全域への横展開が図られる。
予定している伴走支援内容(非資金的支援)
- 今回コンソーシアムとして連携している佐賀県社会福祉協議会による地域社会福祉協議会との連携などの支援
- 地域連携となる事業者、団体等とのつなぎ
- 実行団体同士の学びと気づきの機会づくり
- 助言、メンター等の専門家の紹介
- ファンドレイジングの助言、地域での循環した資金作りのサポート
そのほかにも、事業計画実現にむけての支援を実施していきたいと考えています。
公募期間・申請方法・申請に必要な書類
公募期間
2025年5月9日(金)〜2025年7月31日(木)17時(厳守)
申請方法
応募申請提出方法:Eメールでの提出
問い合わせ
一般社団法人 さが・こども未来応援プロジェクト実行委員会
〒840-0027 佐賀市本庄町本庄1313番地 佐賀女子短期大学3号館内
TEL:090-9482-4434
Email:kyumin2024@saga-codomo.com
公募説明会・相談会
公募説明会
実施日
第一回:5月14日(水) 11 :00~12:00
第二回:5月22日(木) 17:30~18:30
会場
ハイブリッドで行います
オフライン:佐賀女子短期大学
オンライン:zoom
内容
休眠預金制度の概要、募集要項等の説明、質疑応答など
申込み方法
下記の申込フォームから、お申込みください。
URL:https://docs.google.com/forms/d/1JnEzkSsjPz0quCQHRCbodBoqgbJWardZwLpZ26nhCbc/preview
個別相談
希望する団体から適時個別相談に対応します。
実施期間
5月23日(金)〜6月27日(金)の期間随時
相談内容例
本事業の内容について
申請書の記載の仕方についてなど
場所
対面もしくはオンライン(必要があれば現地にお伺いします)
個別相談申込み方法
kyumin2024@saga-codomo.comに「個別相談の希望」のメールをお送りください。お電話などで日程と場所をご相談いたします。
審査
実行団体の審査会
8月上旬〜8月中旬実行団体の審査
- プレゼンテーション及び審査員による質問
応募団体によるプレゼンテーションを対面で予定しています。※1時間程度 - 審査会
提出いただいた資料とプレゼンテーションを元に外部審査員による審査会を通して決定いたします。
内定通知
8月下旬
実行団体決定、契約締結、助成事業開始
9月中旬〜10月上旬
選考は、公平で公正な選考を行うため、第三者の外部有識者・専門家等から構成される審査会において行います。
プレゼン審査では、選定基準に沿ってご説明ください。(プレゼン時間 15分(PPT 15枚程度)
応募書類、申請内容等の確認のため、追加で面談をさせていただく場合があります。その際は、日程調整等のご協力をお願いいたします。
提出書類の不備がある団体は、審査の対象にならない場合があります。申請書類は複数ありますので、申請前に必ず確認の上、ご申請をお願いします。
審査結果は、メールにて通知します。
申請に必要な書類
<申請様式>
申請は、以下の書類に申請内容を記載いただきます。
■ 指公募事業節毎回動画
第二回:5月22日(木) 17:30~18:30の公募事業説明会の実施後アップロードします。
※申請書類は複数ありますので、申請前に必ず確認の上、ご申請をお願いします。提出書類の不備がある団体は、審査の対象にならない場合があります。
選定基準等
1)実行団体は、以下の選定基準に基づき選定を行います。
- 実行団体の選定に当たっては、社会的成果の最大化の観点を重視します。また、社会の諸課題解決の手法の多様性、団体の多様性にも留意した対応の観点から、特定の地域に偏らないように配慮するとともに、運営主体のバランスについて考慮する場合があります。そして、優先的に解決すべき社会の諸課題の分析及びその解決の取り組みにあたっては、ジェンダー平等、社会的弱者への支援等、社会の多様性に十分配慮します。さらに、分野の垣根を越えた関係主体の連携を伴う民間公益活動や、ICT等の積極的活用等、民間の創意と工夫が具体的に生かされており、革新性が高いと認められる実行団体を優先的に選定します。
- 選考にあたっては、申請書類・プレゼンテーション、面談などを予定しています。
- ガバナンス・コンプライアンス(事業計画書に示す事業を適確かつ公正に実施できるガバナンス・コンプライアンス体制等を備えているか)
- 事業の妥当性(社会状況や課題の問題構造の把握が十分に行われており、資金分配団体が設定した課題に対して妥当であるか)
- 実行可能性(業務実施体制や計画、予算が適切か)
- 継続性(助成終了後の計画(支援期間、出口戦略や工程等)が具体的かつ現実的か)
- 先駆性(革新性) (社会の新しい価値の創造、仕組みづくりに寄与するか)
- 波及効果(事業から得られた学びが組織や地域、分野を超えて社会課題の解決につながることが期待できるか)
- 連携と対話(多様な関係者との協働、事業の準備段階から終了後までの体系的な対話が想定されているか)